スタッフブログ _STAFF
田舎暮らしの現実 epsode3 :コミュニティ 田舎の行事
- おんせん県おおいた
- 大分県
- 田舎暮らし
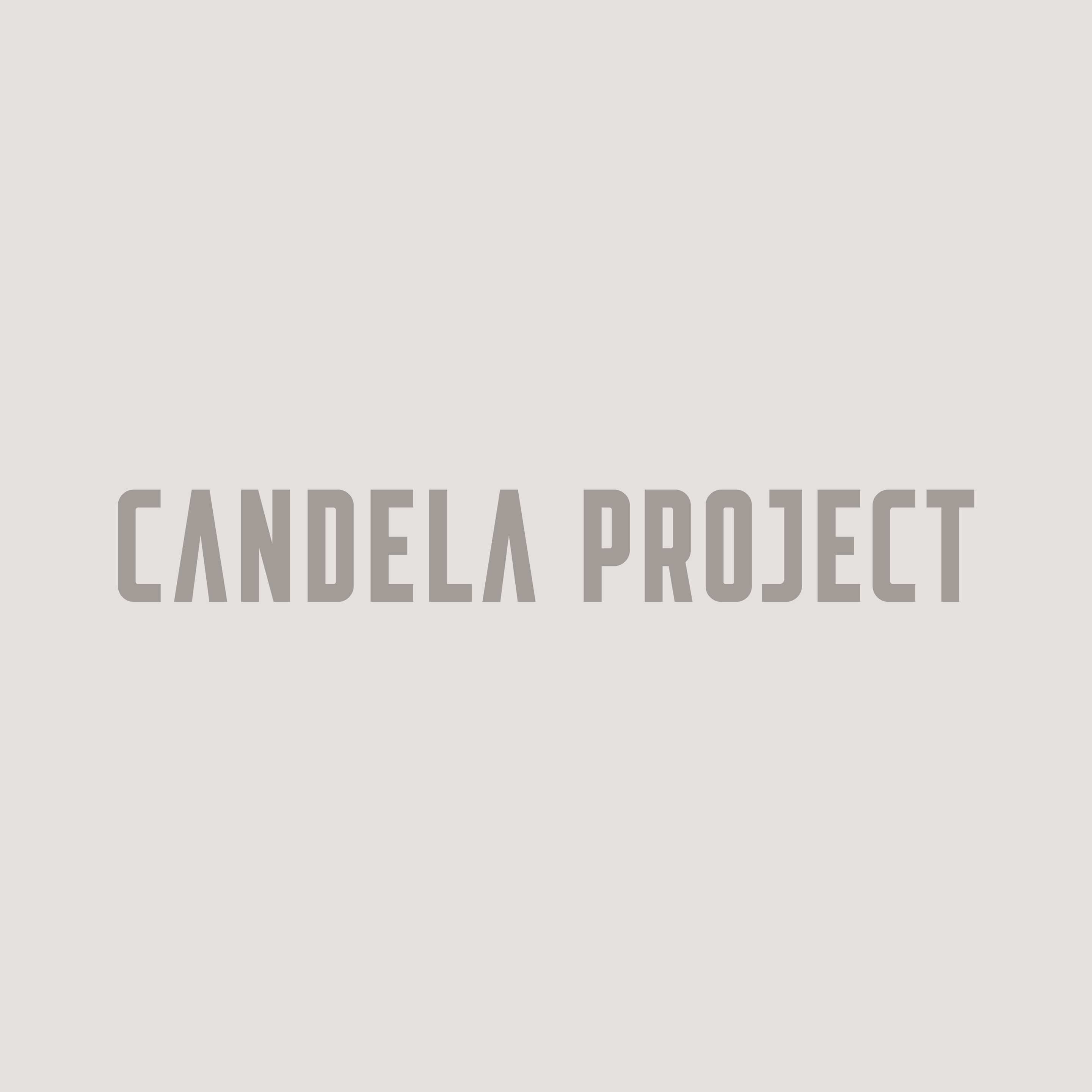
epsode3 :コミュニティ
コロナ禍で田舎の行事(しきたり)が大きく一変しました
田舎暮らしを始めた頃、「お日待」と言う行事がありまして
父は「お日待」の主催者の時だったと思いますが
「お日待」があるからと孫の結婚式を欠席した程です
班で回り番で 12/1の朝のお日様に健康と豊作のお礼をして
焼肉パーティー、昼ごはんを食べたら三三五五解散する
確かに太陽光がなかったら作物は育たないし、
人間も生きて行けないだろう
理にかなった行事だと思うが主催者になった時が大変だった
その後老夫婦の順番になったとき他班に倣って 行事をなくすことになって
この行事は男性が出席するもので 女性は”庚申様”と言うのがあったが
こちらもメンバー減少で後になくなることになる
地区の人が亡くなると通夜の前に「物言い」と言ってお悔やみをいう為に集まる
そこで班長さんが喪主と事前に取り決めた通夜、葬儀日程を発表する
今で言うと喪主がやることではないかと疑問を生じると思うが
以前は自宅で葬儀をしていて 会葬者への御斎から精進上げまで
地区の女性が料理していた
その頃は土葬していた為、男性が墓掘りした
私が20代の頃、父の実家の祖母の自宅葬を覚えている。
それで班長が葬儀委員長のように仕切っていた名残だろうと思う
今では葬儀社が御斎から精進上げまで全て執り行うので
地区の女性は配膳で活躍するが
男性は受付で群がっているのみ
私の母が亡くなったのはコロナ禍前であった
病院で亡くなりそこから葬儀社に連絡すると
葬儀場まで連れて帰ってもらい
お寺さんへの枕経の手配とガイドしてくれる
自分で葬儀社と話をして通夜や葬儀日程を決め区長さんに伝えた
これが間違いで班長さんへ伝えなおした
班長さんに伝えたところ親戚が先だ
それから親戚に伝えた。
地区のルールに反していた。
それから夏場だったので葬儀社に早めに納棺してもらい控室に安置した
ところが一度家に連れて帰るべきだと親戚から声が上がり
夏場なので安置しておきたいと言ったが
父も説得され他の親戚からも言うことを聞いておけと言われ
葬儀社へ無理を言って連れて帰り 実家で一夜を過ごした
年の暮れに「寂し見舞い」と称して亡くなった家にお参りに行く
ここからはどこでも行う事ですが命日から49日目に四十九日、
翌年のお盆に初盆まで行ったが
亡くなって1年目に一周忌、亡くなって二年目の三回忌はコロナ禍で中止した
今年は亡くなって6年目の七回忌、
親戚から簡素に行ってはどうかとの提案通り行う予定。
その後 他家にも不幸があったがコロナ禍のせいで家族葬が多かった
コロナ明けでも病院で亡くなるケースが多く
自宅での「物言い」や「通夜」には出くわしていない。
「物言い」も葬儀社控室に出向て行い、
常会で年末の「寂し見舞い」は正式になくすことに決まった。
しかし、班長が地区の人たちに家族葬or通常葬の連絡、
通常葬の場合は加勢(手伝いの要否)、
地区の人の葬儀社マイクロバスでの送迎など
喪主に代わって行う
これは近くに親戚が少ない方など本家の負担軽減にはなると思う
→ epsode5 につづく




