スタッフブログ _STAFF
「田舎暮らし」spin off;ご先祖様
- おんせん県おおいた
- 大分県
- 栗農家
- 田舎暮らし
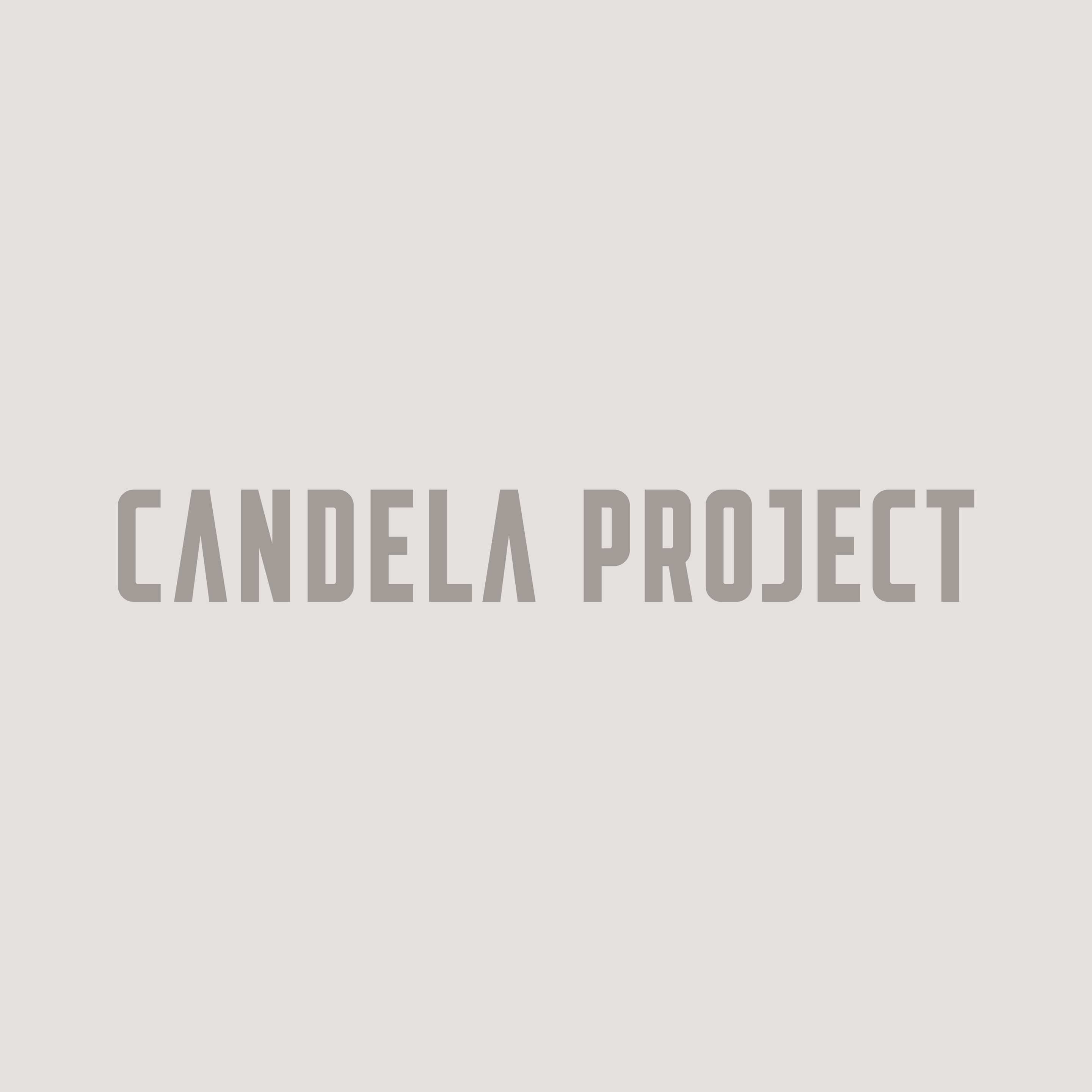
ブログ「田舎暮らし」spin off;ご先祖様
以下は司法書士さんお願いする前に
自力で解決できないかチャレンジした事柄である
父が納税管理人となっている親族名義の土地について
市役所から個人情報保護法により
当家からは戸籍取得出来ないことがはっきりした後
同一氏(うじ)統一墓(戸籍を取得出来ない3名の内2名の墓が存在)
清掃もしているし何か関係性はあるだろうと考えた
ネットではお寺には亡くなった方が記録されている(過去帳)
明治以前は戸籍代わりとされていたとあった
菩提寺に事情を説明して
「過去帳(生前の名前、戒名、死亡年月日が記載)見せてもらえませんか」
と尋ねたところ
「直系の方の分はお見せすることは出来ます
又火事で焼失した分もあるのでご期待に沿えないかも知れません」
こちらも個人情報保護法が効いている。
何か手掛かりがないかと思案していたところ
以前父から当家と同一氏の統一墓内に墓碑があることや
当家と同一氏系図が 長老宅で引き継がれているという話を思い出した
長老宅(お父さんが長老であってお亡くなりなっている)に
事情を説明して見せてもらった
帯状の和紙に右から左へ追記しながら歴代当主が書かれていて
赤いラインで その当主を親子や兄弟であったりを結んでいる。
複数の家族を記しているため 赤いラインが何本もあり
ちょっと見ただけでは繋がりがわからない。
和紙が切れていて私より前に この巻物を開いた方が
間違って巻いたようなところもある。
和紙が痛んでいるので傷つけないように気を付けながら
赤いラインをたどって系図をツリー上に書き換えた。
系図は江戸元禄年から明治初期まで8代に渡って記載されていて
戸籍制度が施行されてから追記が止まっている。
それから160年近く経過しているので戸籍謄本と突き合わせると
高祖父がかろうじて記載されている程度。
5代の記載がなく、探している3名との関係性は判明しなかった。
明治初期(系図の最後の段階)で15軒の同一氏があり現在は8軒に半減している。
これから更に減少するだろう。
よく養子3代続くと言われるが祖父、父、私と養子である。
今回のことで高祖父、曾祖父も養子であることがわかった。
こうやって家を維持してきたのであろう。
「合い年始」「お日待」、不幸があった時の「物言い」「寂し見舞い」、
同一氏(うじ)統一墓清掃と絆を深めあう行事も減少して
山川は昔のままながら人の心は変わりつつあるなと思いを馳せている。
この系図は2つの巻物で構成されており現代に近い方を見た。
もう一つは当家氏(うじ)の成り立ちのようなものである。
又、現代に近い系図には1655年明暦年に現在の竹田市九重野から
当地区へ移住した旨の前書きがあり
このことは当家氏統一墓にある墓碑にも同内容が刻まれていた。
長老宅から同じ先祖を持ち他地域に移住した子孫が
モニュメントを作っているよと場所を教えてくれた。
そのモニュメントには先祖は宮崎県高千穂、大分県竹田市九重野に跨る地域の豪族で
緩木山にある緩木城の勤番として
平氏、大友氏と代々仕えた武士であった。
キリシタン大名として知られる大友宗麟がキリスト教を保護、
信仰するあまりに神社仏閣を取り壊していった。
このことに部下ながらたまりかねて諫言した為、
城を攻撃され果てた(天正の乱)。
子孫は九重野の地に落居帰農した。
その後大分県南西部の何か所かに分家、移住をしている。
その一つが当地区であることが分かった。
このことを二人の子供の母となっている娘に話すと
「ああ武士で良かった。ご先祖様はてっきりお百姓さんと思っていた」と
そこへすかさず妻が「あなた(私のこと)は養子でしょ。血のつながりはないわよ」
いずれにしてもそのことを知り
何か背筋を伸ばして暮らしてくれればそれでいいと思う。




